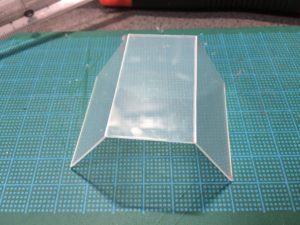電子工作の続きです。
前回作った「電源アダプタの通電検査装置」、
基盤むき出しのままなので、簡易に筐体を作って納めてみようと思います。
それが今回のお題です。
<完成写真>
<準備>
-
材料

-
電源アダプタの通電検査装置
- 前回「電子工作に挑戦」で作ったものです。
-
材木(端切れ/9×45)
- 基盤の幅に合わせて切って、土台にします。
- 基盤の幅が20mmなので、やや広く25mmの幅で切り出します。
-
ポリプロピレンのシート(端切れ/厚み0.75mm)
- 筐体のカバー部分にします。
- 内部が見えるように「クリア」の素材を選択します。
-
基盤の高さが約17mmなので、カバーの高さは17+9=26mmで、
ちょっと大きめに30mmとりましょう。
すると、30+25+30=85mmの長さが必要です。
奥行きは、土台の45mmです。
-
タッピングねじ(ステンレス/トラス頭/2×10mm)
- 筐体のカバーを土台に留めるのに使います。
-
土台の厚みが9mmしかないので、
ねじの太さはなるべく細い方が良いでしょう。 -
土台の両側からねじを入れますから、
25÷2=12.5mm以下の長さにしないと、干渉してしまいます。
-
タッピングねじ(ステンレス/鍋頭/2×14mm)
- 基盤を土台に留めるのに使います。
- 太さは、基盤のねじ穴に合わせます。
-
長さは、基盤の厚みが約1.5mmで、スペーサーが4mm、
土台が9mmなので、1.5+4+9=14.5mmより短く、
1.5+4=5.5mmより長いものを選択します。 - ねじが土台を突き抜けてしまわないように計算します。 14-5.5=8.5mm土台に刺さり、0.5mm残る計算です。
-
このサイズのねじは入手し辛いようです。
私は「MISUMI」で購入しました。
-
ポリエチレンチューブホース(内径2×外径4mm)
- これを短く切って、スペーサーにします。
-
電源アダプタの通電検査装置
-
道具

-
カッターガイド
- カッターで直線を切るのに使います。
-
普通の直尺を使うと、ズレやすいし、怪我をしやすいです。
きちんとしたカッターガイドを使う事をお勧めします。 -
刃が当たる部分がアルミやプラ製のものは、
直ぐに削れて凸凹になってしまいます。
ステンレスなどの比較的堅い素材のものがお勧めです。 - 指先を怪我から守る、ガードレール付きのものをお勧めします。
-
カッターガイドは自作する事もできます。
「【自作】保護付きカッターガイド」、
「『600mm級の透明カッターガイド』の材料を小分け売り」で
紹介しています。
-
カッティングマット
- 「カッターマット」とも言います。
- 他のもので代用すると失敗しがちなので、正式なものを使いましょう。
-
プラスチックカッター
- ポリプロピレンのシートに折り溝を掘るのに使います。
- 写真に写っているのは、「オルファ」の「PカッターL型 205B」です。
-
カッター
-
ポリプロピレンのシートや
ポリエチレンチューブホースを切り出すのに使います。 -
普通のカッターです。
グリップが太くて握りやすいものが作業し易いです。 -
私は、百均製の「ガワ」に
「オルファ」の「特専黒刃(大)」を入れて使っています。
-
ポリプロピレンのシートや
-
油性ペン(超極細/赤)
- ねじ位置や切断線などを印すのに使います。
-
写真に写っているのは
「ゼブラ」の「マッキーケア超極細 YYTH3-R 赤」です。
-
ドライバー
- ねじを締めるのに使います。
- 今回は、電動だと強すぎるので、普通のドライバーで手作業でします。
-
ミニルーター
- ねじの下穴を空けるのに使います。
-
ドリル刃(1.4mm)
- ねじの下穴を空けるのに使います。
-
下穴はねじ径の70%が目安です。
2.0×70%=1.4mm
-
ビニルテープ
- ドリル刃に下穴の深さの目安を印すのに使います。
-
ピンセット
- 細かいパーツを摘むのに使います。
-
C型クランプ
- ねじを締める時の「割れ」防止に使います。
-
当て木(段ボール)
- C型クランプと材料の間に挟んで、傷が付くのを防止します。
-
ハサミ
- 普通のハサミです。
- ビニルテープなどを切るのに使います。
-
マスキングテープ(木部用)
- 材料を仮止めするのに使います。
-
スケール
- 寸法を測るのに使います。
- 今回は、コンベックスタイプが使い易いでしょう。
-
当て木
- 下穴を空ける際に、念のため下敷きにします。
-
ホビーのこ(写真撮り忘れ)
- 基盤を切るのに使います。
- 私のお気に入りは「オルファ」の「ホビーのこ 167B」です。
-
ホビーのこ用ガイド(自作品/写真撮り忘れ)
-
真っ直ぐ綺麗に切るのに重宝します。
私はガイドなしで真っ直ぐ切れる腕があるとは思っていませんし。 - 『「ホビーのこ」用の鋸ガイドを自作する』で作った自作品です。 ホビーのこ向けの小さいガイドは売ってないようなので。
-
真っ直ぐ綺麗に切るのに重宝します。
-
三角刀(写真撮り忘れ)
-
折り溝をプラスチックカッターで掘った時の
「バリ」を除去するのに使います。 - やり方の「コツ」は「プラスチックのシートに折り溝を掘る」で図付きで紹介しています。
-
折り溝をプラスチックカッターで掘った時の
-
電源アダプター(写真撮り忘れ)
- 最終的にこれを繋いでLEDが正常に点灯するか、再度確認します。
-
カッターガイド
<工程>
-
まず、基盤の裏側部分の高さを測ります。
- その高さ分のスペーサーが必要になるわけです。
- 約3mmほどだったので、スペーサーは余裕を見て4mmにする事にします。
-
ポリエチレンチューブホースを切って、スペーサーを作ります。

- 基盤の無駄な部分を切り捨てます。
- 土台を切り出します。
-
土台にねじ穴の位置を印します。
-
土台の上にそっと基盤を乗せて、
ねじ穴を通して油性ペンで「ちょん」と突っついてやると上手くできます。
-
土台の上にそっと基盤を乗せて、
-
下穴の深さに合わせて、ドリル刃に目安を印します。
- 基盤の厚みとスペーサーの高さを差し引いた「有効長」を印します。
-
ねじは食い込み易いように先端が細っていますが、
その部分を除いた、同じ太さが続く長さが「有効長」です。
- 土台に、ねじの下穴を空けます。
- 基盤を土台に留めます。
-
カバーを切り出します。
-
ポリプロピレンのシートに切断線と折り溝線を描いたら、
先に折り溝を掘ってしまった方がやり易いです。-
この時、プラスチックカッターを使うのですが、
一度に掘り切ろうとすると失敗しがちです。
軽く何度かなぞって、目的の深さまで掘り進める方が確実です。 -
深く掘りすぎると、簡単に千切れてしまいます。
深さの加減が分からない人は、
端切れを使って何度か練習して感覚を掴みましょう。
-
この時、プラスチックカッターを使うのですが、
-
折り溝を掘った時の「バリ」を除去します。
- やり方の「コツ」は「プラスチックのシートに折り溝を掘る」で図付きで紹介しています。
-
今回は、普通のカッターで切断します。
- 一度に切りきろうと思わず、何度かなぞって切るようにしてやります。
-
ポリプロピレンのシートに切断線と折り溝線を描いたら、
- 切り出したカバーを折り溝に沿って谷折りします。
-
マスキングテープで、土台にカバーを仮止めします。
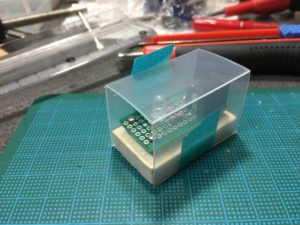
-
下穴の深さに合わせて、ドリル刃に目安を印します。
- カバーごと貫いて空けるので、単純にねじの「有効長」を印します。
-
ねじは食い込み易いように先端が細っていますが、
その部分を除いた、同じ太さが続く長さが「有効長」です。
-
土台の側面にカバーごと貫いて、ねじの下穴を空けます。
-
この時、基盤を土台に留めたねじの位置を避けて空けないと、
干渉してしまいますので位置をよく見定めて下さい。
-
この時、基盤を土台に留めたねじの位置を避けて空けないと、
- カバーごとねじを締めます。
-
仮止めしていたマスキングテープを剥がします。
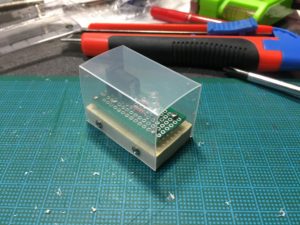
-
電源アダプターを実際に繋いで、正常にLEDが点灯するのを確認したら完成です。

<今後の予定>
本題である「換気ファン」を作ります。
ドアの通気口を外して、そこに収める計画です。


 予定では、PC用の80mm角の冷却ファンを8個並べて、
予定では、PC用の80mm角の冷却ファンを8個並べて、
ドアの通風口に収まる形にするつもりですが、
先に、ファンを1個だけで仮組みします。
それで正常に動作すれば、残りの7つを追加して、
隙間を埋め、基盤をカバーするように蓋をします。
あと、電源アダプターが、壁のコンセントまで直接届かないので、
延長コードの取り回しもしなくてはなりませんし、
それをモールで整頓しないといけません。
・・・結構大掛かりな作業になりますね。(;´Д`A
暑い季節が終わらないうちに仕上げないと、有り難みが薄れてしまうのですが。
何週掛かるか見当もつきません。orz
お気に召しましたら、一票(ワンクリック)下さい。ランキングに参加しておりますゆえ。
 人気ブログランキング |
 手作り・DIYランキング |
|
|
|
|